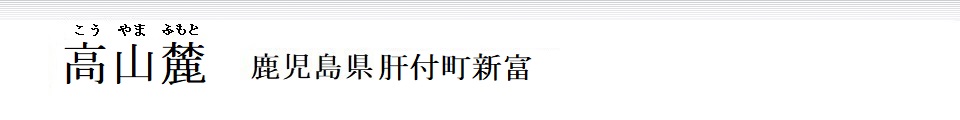鹿児島県と宮崎県に残る旧薩摩藩領内の外城と麓の町並み記録です。
高山(こうやま)は,大隅の豪族・肝付氏の本拠地で,流鏑馬(やぶさめ)の町として知られます。藩政時代は高山郷と呼ばれ,高山郷の中心・新富に地頭仮屋が置かれました。高山麓を歩くと,古い武家門やイヌマキ,生垣の続く街路が広がり,麓らしい町並みが残っています。

高山麓の町並み(2008年)
大隅の豪族・肝付氏の歴史は古く,安和2年(967年)に薩摩国に下向した伴兼行に遡ります。伴兼行の孫・兼貞が大隅国肝属郡弁済使となると,子・兼俊が高山に移り住み,肝付氏を名乗りました。以後、肝付氏は高山城を居城とし,大隅一円に勢力を拡大します。高山城が廃城となり,高山が島津氏の直轄領となると,支城・弓張城の麓に地頭館が設置され,周囲に麓集落が形成されました。

役場前の街路(左)と肝付町役場(右)
高山麓は高山川の東岸に町割りが計画的に作られており,地頭仮屋を中心に南北および東西に複数の街路が延びています。屋敷地は広く,街路に沿って生垣や石垣が続く町並みが残っています。


高山麓の武家門
腕木門。役場前の街路(十文字馬場)に建つ。左右に小屋根を備える立派な門。観音扉に潜り戸付き。後方に控え柱が見える。


高山麓の武家屋敷
石柱門。イヌマキと築山の植え込みが素晴らしい。

肝付町役場前の街路
十文字馬場。南北に延びる街路に沿って生垣が続き,屋敷林が残る。

日高家武家門(2013年)
腕木門。役場前の街路に建つ。乳鋲付きの観音扉に潜り戸付き。修復後の姿が南日本新聞のカラー記事に紹介された。主屋根の左右に小屋根、袖がつく立派な構えである。二階堂家武家門とともに高山麓のシンボル的武家門。

肝付町役場前の町並み
日高家武家門の目の前,肝付町役場に隣接する高山小学校が地頭仮屋跡。

高山麓の町並み
役場前の街路から東西に延びる街路。生垣の続く町並みが残っている。

高山麓の武家門
腕木門。上の街路に残る。こちらも左右の小屋根に袖がつく構え。

高山麓の町並み
役場前の街路と平行に南北に延びる街路に石垣と生垣が続き,古いイヌマキが見られます。
高山は流鏑馬(やぶさめ)の町。流鏑馬は鎌倉時代から続く秋の行事。鹿児島県内では肝付町の四十九所神社,曽於市の住吉神社,日置市の大汝牟遅神社で行われます。


宮之馬場(やぶさめ参道)
弓張城跡の麓にある四十九所神社から参道が南北に延びる。流鏑馬(やぶさめ)は,装束姿の若武者が参道を疾走する馬に乗りながら鏑矢で的を射る武術で,毎年秋に行われる四十九所神社の神事です。


四十九所神社
四十九所神社は,大宰府の大監であった大伴兼行が下向した際に伊勢の両宮を勧請して創建されたと言われる。肝付氏の守護神として栄えた。

高山護国神社(左)と石柱門(右)
護国神社は,戊辰の役をはじめとして戦没者を祀る。


新富の町並み
上の街路は宮之馬場と平行に南北に延びる。ここでも街路に沿って生垣や石垣が続き、石柱門が見られる。
肝付氏について
肝付氏は,12世紀から400年間にわたり大隅北部を支配し,宗家16代兼続のときに領土を最大化し,戦国大名に成長します。その後,島津氏との抗争に敗れると,薩摩・阿多に移封され,大隅の地から離れます。宗家は没落しますが,肝付氏の庶流は早くから島津氏に重用され,江戸期の喜入領主・肝付氏は島津家の家老を務め,幕末から明治維新にかけて活躍する肝付尚五郎(小松帯刀)が生まれます。
訪 問:2008年10月24日(一部2011.6,2013.9)
備 考:二階堂家住宅,野町,高山麓に残る武家門は4棟。
参 考:肝付町HP,きもつき情報局,鹿児島県の歴史
| 戻る|
|ホーム|
戻る|
|ホーム|

高山麓の町並み(2008年)
大隅の豪族・肝付氏の歴史は古く,安和2年(967年)に薩摩国に下向した伴兼行に遡ります。伴兼行の孫・兼貞が大隅国肝属郡弁済使となると,子・兼俊が高山に移り住み,肝付氏を名乗りました。以後、肝付氏は高山城を居城とし,大隅一円に勢力を拡大します。高山城が廃城となり,高山が島津氏の直轄領となると,支城・弓張城の麓に地頭館が設置され,周囲に麓集落が形成されました。

役場前の街路(左)と肝付町役場(右)
高山麓は高山川の東岸に町割りが計画的に作られており,地頭仮屋を中心に南北および東西に複数の街路が延びています。屋敷地は広く,街路に沿って生垣や石垣が続く町並みが残っています。


高山麓の武家門
腕木門。役場前の街路(十文字馬場)に建つ。左右に小屋根を備える立派な門。観音扉に潜り戸付き。後方に控え柱が見える。


高山麓の武家屋敷
石柱門。イヌマキと築山の植え込みが素晴らしい。

肝付町役場前の街路
十文字馬場。南北に延びる街路に沿って生垣が続き,屋敷林が残る。

日高家武家門(2013年)
腕木門。役場前の街路に建つ。乳鋲付きの観音扉に潜り戸付き。修復後の姿が南日本新聞のカラー記事に紹介された。主屋根の左右に小屋根、袖がつく立派な構えである。二階堂家武家門とともに高山麓のシンボル的武家門。

肝付町役場前の町並み
日高家武家門の目の前,肝付町役場に隣接する高山小学校が地頭仮屋跡。

高山麓の町並み
役場前の街路から東西に延びる街路。生垣の続く町並みが残っている。

高山麓の武家門
腕木門。上の街路に残る。こちらも左右の小屋根に袖がつく構え。

高山麓の町並み
役場前の街路と平行に南北に延びる街路に石垣と生垣が続き,古いイヌマキが見られます。
高山は流鏑馬(やぶさめ)の町。流鏑馬は鎌倉時代から続く秋の行事。鹿児島県内では肝付町の四十九所神社,曽於市の住吉神社,日置市の大汝牟遅神社で行われます。


宮之馬場(やぶさめ参道)
弓張城跡の麓にある四十九所神社から参道が南北に延びる。流鏑馬(やぶさめ)は,装束姿の若武者が参道を疾走する馬に乗りながら鏑矢で的を射る武術で,毎年秋に行われる四十九所神社の神事です。


四十九所神社
四十九所神社は,大宰府の大監であった大伴兼行が下向した際に伊勢の両宮を勧請して創建されたと言われる。肝付氏の守護神として栄えた。

高山護国神社(左)と石柱門(右)
護国神社は,戊辰の役をはじめとして戦没者を祀る。


新富の町並み
上の街路は宮之馬場と平行に南北に延びる。ここでも街路に沿って生垣や石垣が続き、石柱門が見られる。
肝付氏について
肝付氏は,12世紀から400年間にわたり大隅北部を支配し,宗家16代兼続のときに領土を最大化し,戦国大名に成長します。その後,島津氏との抗争に敗れると,薩摩・阿多に移封され,大隅の地から離れます。宗家は没落しますが,肝付氏の庶流は早くから島津氏に重用され,江戸期の喜入領主・肝付氏は島津家の家老を務め,幕末から明治維新にかけて活躍する肝付尚五郎(小松帯刀)が生まれます。
訪 問:2008年10月24日(一部2011.6,2013.9)
備 考:二階堂家住宅,野町,高山麓に残る武家門は4棟。
参 考:肝付町HP,きもつき情報局,鹿児島県の歴史
|
Copyright (C) Tojoh Archives. All Rights Reserved.