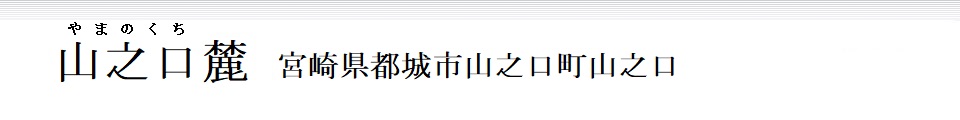鹿児島県と宮崎県に残る旧薩摩藩領内の外城と麓の町並み記録です。
山之口麓は都城盆地の旧山之口町にある小さな麓です。藩政時代の山之口郷は,当初都城島津家の私領地でしたが,薩摩藩の財政の逼迫から,慶長19年(1614)に藩の直轄領となり,山之口郷の中心・山之口村に地頭仮屋が置かれ,薩摩藩から派遣された地頭が政務を行いました。山之口麓には野積の石垣や武家門など往時の遺構が今も残っています。

地頭仮屋跡(人形の館)
地頭仮屋跡は国道269号線(鹿児島街道)沿いにあり,山之口町の旧役場もここに置かれました。現在は山之口麓に伝わる文弥節人形浄瑠璃の資料館(通称人形の館)が建っています。文弥節人形浄瑠璃は,島津の殿様の参勤交代の際に山之口の郷士が京・大坂で習い覚えて持ち帰ったと伝えられており,保存会によって毎年定期公演が行われています。

山之口麓の町並み(2007年)
山口麓への初訪門は2007年夏の宮崎旅行の際。滞在時間は短かったが麓地区内に複数の武家門を確認することができました。上の古い武家門は現在見られません。

山之口麓の町並み
麓地区の中心を東西に直線街路(旧街道)が延びており,左右に石垣や生垣が見られます。旧街道に対し南北に交差する複数の街路も残っており,麓地区が計画的に町割りされたことが分かります。

山之口麓の武家門
腕木門。左右に小屋根と袖がつく。最初に挙げた門とは別の武家門です。屋敷内の建物は古民家レストランとして利用されています。イヌマキも実に立派。

山之口麓の武家門

山之口麓の町並み
写真にはないが,山之口の麓地区には入来麓を彷彿させる野積みの石垣で区画された町割りも残っています。

石柱門(左)と武家門(右)
山之口の麓地区には古い石柱門も見られます。右の武家門は比較的新しい。

地頭仮屋跡
弥五郎どん伝説について
弥五郎どんは宮崎県と鹿児島県に伝わる巨人伝説です。古代の天皇に仕えた武内宿禰をモデルとする説,720年(養老4年)に南九州で起きた隼人の乱の指導者をモデルとする説があります。弥五郎どん祭りは隼人の霊を供養するため720年に宇佐宮(宇佐神宮)が行った放生会が由来とされ,毎年11月に宮崎県の2箇所(山之口町・的野八幡宮、日南市・田神八幡神社)と鹿児島県の1箇所(曽於市・岩川八幡神社)で盛大に行われています。三体それぞれ衣装に趣向が凝らされ,見た目がまるで異なっているところが興味深い。
訪 問:2008年8月5日(一部2007年8月)
備 考:山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館。弥五郎どんの館。山之口麓に残る武家門は2棟。
参 考:都城市HP,曽於市HP,宇佐神宮HP等
| 戻る|
|ホーム|
戻る|
|ホーム|

地頭仮屋跡(人形の館)
地頭仮屋跡は国道269号線(鹿児島街道)沿いにあり,山之口町の旧役場もここに置かれました。現在は山之口麓に伝わる文弥節人形浄瑠璃の資料館(通称人形の館)が建っています。文弥節人形浄瑠璃は,島津の殿様の参勤交代の際に山之口の郷士が京・大坂で習い覚えて持ち帰ったと伝えられており,保存会によって毎年定期公演が行われています。

山之口麓の町並み(2007年)
山口麓への初訪門は2007年夏の宮崎旅行の際。滞在時間は短かったが麓地区内に複数の武家門を確認することができました。上の古い武家門は現在見られません。

山之口麓の町並み
麓地区の中心を東西に直線街路(旧街道)が延びており,左右に石垣や生垣が見られます。旧街道に対し南北に交差する複数の街路も残っており,麓地区が計画的に町割りされたことが分かります。

山之口麓の武家門
腕木門。左右に小屋根と袖がつく。最初に挙げた門とは別の武家門です。屋敷内の建物は古民家レストランとして利用されています。イヌマキも実に立派。

山之口麓の武家門

山之口麓の町並み
写真にはないが,山之口の麓地区には入来麓を彷彿させる野積みの石垣で区画された町割りも残っています。

石柱門(左)と武家門(右)
山之口の麓地区には古い石柱門も見られます。右の武家門は比較的新しい。

地頭仮屋跡
弥五郎どん伝説について
弥五郎どんは宮崎県と鹿児島県に伝わる巨人伝説です。古代の天皇に仕えた武内宿禰をモデルとする説,720年(養老4年)に南九州で起きた隼人の乱の指導者をモデルとする説があります。弥五郎どん祭りは隼人の霊を供養するため720年に宇佐宮(宇佐神宮)が行った放生会が由来とされ,毎年11月に宮崎県の2箇所(山之口町・的野八幡宮、日南市・田神八幡神社)と鹿児島県の1箇所(曽於市・岩川八幡神社)で盛大に行われています。三体それぞれ衣装に趣向が凝らされ,見た目がまるで異なっているところが興味深い。
訪 問:2008年8月5日(一部2007年8月)
備 考:山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館。弥五郎どんの館。山之口麓に残る武家門は2棟。
参 考:都城市HP,曽於市HP,宇佐神宮HP等
|
Copyright (C) Tojoh Archives. All Rights Reserved.